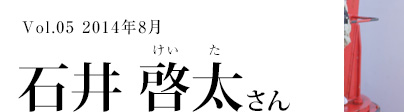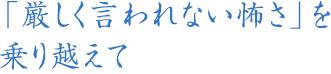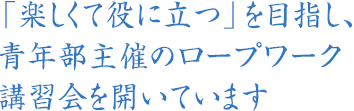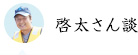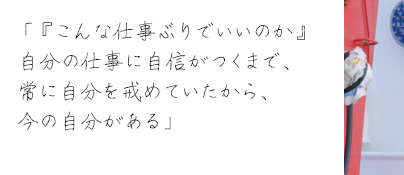


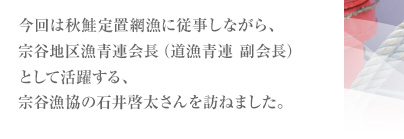


啓太さんは、東京生まれの札幌育ち。漁師になるまでは、札幌で大手量販店の大規模店にある水産コーナーで修業し、やがて仕事ぶりが認められ、小規模店の水産コーナーを任せてもらうまでになりました。しかし途中採用だったこともあり正社員への道は厳しく、二十代後半には、自分の進む道を再び考えるようになりました。実は啓太さんの祖父は漁協系統運動の実践者として知られた宗谷管内の組合長でしたが、石井さんの父親は跡を継がずに水産物の貿易関係の仕事についていました。
漁師として務まるか、決心を固めるため2年間祖父の漁業部で若い者として働きました。「今思うと、孫が使い物になるのか見極める、祖父の試験期間だった」と啓太さんはふりかえります。試されることになった2年の秋鮭漁期間は、どんなに波が高くても船に酔わず、仕事に取り組めたことが漁師になる決め手でした。父親は啓太さんの決断に反対はしませんでしたが、「覚悟を決めて宗谷に行け」と送り出してくれたそうです。

浜育ちであれば親や祖父が師匠であり、厳しい修業を経て一人前になりますが、啓太さんは親方の跡継ぎとして扱われ、船頭や先輩漁師から厳しい言葉を聞くことはありませんでした。「きっと言いたいことの半分も言われていない」「こんな仕事ぶりでいいのか」自分の仕事に自信がつくまで、常に自分を戒めていたから、今の自分があると話してくれました。

宗谷の浜にも跡継ぎとなりそうな若者は大勢います。でもなかなか青年部に入ってこないのが現実。今は漁師の修業も様変わりし、「見て覚えろ」の時代ではありません。そこで、初心者からベテランまで参加して役に立つような、ロープワークや網修理の技術が学べるよう、稚内の普及所や組合の協力を得て、講習会を開催しています。終了後は焼き肉パーティをして盛り上がりますが、焼き肉目当てでも構いません。みんなで企画してやり遂げることで何かを学ぶはずです。
何も言わなかった祖父でしたが、一度だけ「時代の流れに敏感になれ」と教えられたことがあります。今となっては真意を聞くことはできませんが、資源を増やして豊かな浜づくりを目指した、祖父の漁師人生を自分なりに勉強し、青年部活動、ひいてはこれからの漁師人生に役立てたいと思います。

啓太さんの自宅で夕食をごちそうになりました。この日網にかかった「しまぞい」「黒ぞい」はじめ、「たこ」「ほたて」に加え、とっておき「鮭のルイベ」。もちろん腕を振るったのは啓太さん。立派な姿造りの刺身の数々にびっくり。鮮魚売り場で磨いた腕は本物です。人生に無駄な修業はありません。プロ顔負けの包丁さばきは、地元の小学生を対象に行っている「漁師さんの出前授業」に生かされています。

東京都豊島区出身の札幌育ち。38歳。
学生生活終了後、車両整備や大手量販店の鮮魚売り場の責任者を経て、祖父が起こした宗谷漁協の石井漁業部へ就職。1級小型船舶操縦士・大型特殊・移動式クレーン・潜水士など資格多数。現在は責任者として秋鮭定置網漁に従事。趣味は車とミニカー収集。保育園の年中さん(4歳)と2歳の二人の男の子の良きパパです。