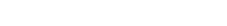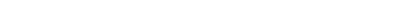北海道が主な生息地となる昆布。北日本沿岸に生育する昆布は、種類や産地の特性によって様々な個性があり、私たちの食卓に並ぶ親しみのある食材だ。生育環境と産地特性に大きく影響され、その特徴によって出汁としてはもちろん、伝統料理やオリジナルレシピにも使われている。昆布は産地の特性を生かすことから、ワインを語るときに使われるテロワールと似ているとされ、日本の海のテロワールとも言えるだろう。

ワインで言う「テロワール」とは風土、土地の個性を意味し、同じ品種のブドウでも栽培される地域ごとに個性の違うブドウが育つことなどをいう。昆布にもこうしたテロワールのようなものがあり、同じ北海道産でもとれる海域によって個性が違い、用途も違ってくるのだ。利尻・礼文島周辺を中心に主にオホーツク海側でとれるのは利尻昆布、知床半島でとれるのが羅臼昆布、渡島地区は真昆布が主体となっている。いずれもだし用高級昆布だが、だしの味わいや色合いが異なる。室蘭から襟裳岬でとれる日高昆布はだしだけでなく煮物にも使いやすい。釧路・根室の沿岸の長昆布は早く柔らかくなるので煮物に、日本海側の細目昆布は強い粘りを生かしてとろろなどに加工される。ほかにも函館沿岸のガゴメ昆布、釧路・根室沿岸の厚葉昆布もあり、北海道の風土が昆布の個性を作り上げた歴史となっている。



北海道の昆布が全国に広まったのは江戸時代。物流を担っていた北前船が大きな役割を果たしており、北前船の航路は「昆布ロード」とも呼ばれていた。北海道で夏に水揚げ・乾燥した昆布が運ばれるのは翌年の春。その間、蔵の中で“むしろ”に包んで保存していたところ、磯臭さが抜けてまろやかな旨味に変わり料理人に喜ばれたという。そうして発達した技術が「蔵囲(くらがこい)」。1年、2年ものなど年数によって味も色も変化し、旨み成分が増して味わい深くなる。ただしどんな昆布でも蔵囲になるということではなく、基本がしっかりした昆布に限られる。まるでワインのヴィンテージだ。現代では少なくなっている蔵囲だが、昆布問屋によって伝統が受け継がれ、昆布の食文化が守られている。



近年昆布の生産量は減産傾向にあるが、日本人の食卓に欠かすことのできない食材だからこそ、漁師さんたちの昆布漁に対する想いは大きい。天日干しの地域では、水揚げしてきた昆布を、風の流れに沿って手作業で1本ずつ綺麗に干場(かんば)並べていく。真っ直ぐに並べて天日干している昆布の風景は、夏の北海道ならではの風物詩だろう。いっぽうで乾燥機を使う地域では天候に左右されずに漁を行うことができる。地域によって種類だけでなく、水揚げや製品作りの方法などが異なるのも大きな特徴と言える。北海道の夏は短い。そのため限られた期間内で美味しい昆布を生産するため、漁師さん達は新たな取り組みを行なっている。
数年前より資源保全活動として実施されている、昆布の生産回復を狙った「どぶ漬けロープ設置事業」。昆布の胞子と海水を合わせた液体にロープをどぶ漬けし、海水に設置する簡易型の養殖試験を全道で始め、北海道の昆布文化を衰退させないために増産を目指している。
2013年世界無形文化遺産として「和食」が登録されたことによって、日本だけではなく世界からも注目されている昆布。日本の伝統的な食文化として、私たちの食卓で大切にしていきたい。