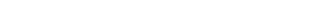川で生まれ海へと下り、再び故郷の北海道へ戻る鮭。郷土料理として各地で食され、大切な北海道の食文化として昔から愛されている。
「東の鮭正月、西の鰤正月」と言われ、東日本で鮭は新年を迎えるお膳にならぶ大切な魚の代表とされていた。いずれも塩蔵処理に適した大きな魚で保存性がよく、海から離れた地域にも運ぶことができ、正月の間食べつなぐことが出来たからだろう。冷凍や輸送技術が進化し、食卓の嗜好が変わってきた現代でも、お正月に新年を祝い、新しい年を迎える喜びの席には、北海道の鮭は欠かすことのできない大切な存在となっている。

秋に塩引きした鮭は正月を迎える頃にほどよく熟成され、余すことなくさまざまな料理に使われてゆく。身は厚めに切って焼き、年越しや新年の膳の主役へ。頭の氷頭はなますに、アラは三平汁に切り分け、尾の方の身は昆布巻きの芯に。秋のうちに塩漬けや醤油漬けしておいたいくらも、子孫繁栄を願う食材として雑煮やなますに添えられる。鮭一尾を切り分けることは、新年を迎えるための年末の伝統的な行事だ。



北海道の食卓に欠かせない味として、鮭を使った「飯寿司」がある。魚と野菜を白飯とこうじで漬け込んだ馴れ寿司の一種で、北海道沿岸地方の家庭では代々伝えられたレシピがあるほどだ。鮭以外に、ホッケ、ハタハタなどさまざまな魚でも作るが、やはり王道は鮭の飯寿司。寒くなってから仕込みを行い、食べごろになるのはちょうど年末からお正月ごろ。紅白の色合いが新年のお祝いにいろどりを添えてくれる。
他にも北海道ならではの食べ方としては「ルイベ」がある。アイヌ語で「溶ける食べ物」を意味するルイベは、ブロック状の鮭の身を凍らせて刺身のように切って食べる。通常天然の鮭は生では食べないため、一度冷凍して食するアイヌ文化の伝統的な食べ方だ。冷凍庫がなかった時代では、屋外で凍らせていたのだろう。北国ならではの寒さを利用し、今も引き継がれている北海道の味だ。
北海道が水揚げ量日本一の鮭。定置網漁を主にほぼ北海道全域で漁獲されている。9月頃から産卵で戻ってきた鮭を「秋鮭」、時期を間違えて夏に北海道に戻ってくる鮭を「時鮭(ときしらず)」と呼び、漁期は秋と夏の年に2回。鮭の水揚げが始まった各地の港は活気づき賑わっている。
平成15年には水揚げ量20万トンを超えた時期もあったが、近年の鮭漁は低調気味に推移している。それでも漁師さんの鮭漁に対する想いはとても熱い!「今までも、輸入物や不漁など幾多の困難を乗り越えて、日本の食卓を守り続けてきた。何より自然の営みの中で生まれ、北海道に戻ってきた鮭の美味しさには自信がある!だからこそ漁を続けることができるのだ」明治時代から操業を引き継いでいる5代目漁師さんがいう。
「鮭が獲れるのはあたりまえではなく、自然の資源に恵まれているからこそ」。資源豊かな海の恵みに感謝して、これからも北海道の食文化としての鮭をいただこう!