
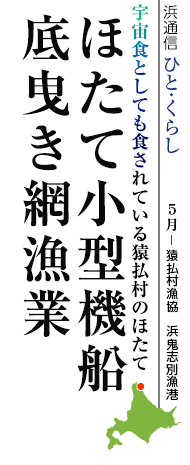
朝4時半、船団は沖の漁場へ向かう。漁場へ着くと、両舷から八尺と呼ばれる漁具を海底へ沈めて底引きをする。八尺の先端の熊手のような爪が海底を耕すように進むと、普段海底の砂に潜っているほたてたちが掻き出されて、袋網の部分で受け取られる仕組みだ。
オホーツク海でのほたて漁は生まれて1年目の稚貝を造成(天敵のひとでや前年に取り残したほたてを取り除くこと)された海底へまき、3年後、つまり4年貝を漁獲するという農業さながらに育てて獲る4輪採制を行っている。この方法をとってから漁獲量が高水準で安定しているという。猿払のほたてと言えばその玉(貝柱)の大きさ、厚さ、そして甘みの強い絶品の旨みで最高級にランクされているが、それは、ここオホーツク海が栄養豊かな海域であり、かつ猿払の沖の海底はほたての生育に適した平らな砂地であり、そこで育つためだ。
八尺の袋網に受け止められたほたてたちは船上で迅速に選別され、出荷できる4年貝は船にあらかじめ敷かれているもっこという網の上に積まれる。そしていっぱいになると次のもっこを敷き、ほたてをその上に積んでいく。ちょうど地層のように積送されていく感じだ。それはほたてをトラックに積み込む際、迅速かつ貝を傷めないための効率の良い方法だ。そしてこの作業を繰り返し、例えば12tなど組合で設定したノルマをクリアすると帰港となる。
帰港時間を組合に報告すると、各漁船に割り当てられたトラックが岸壁へ移動し荷揚げの準備を整える。漁船が接岸すると、船上のクレーンを使い、もっこ毎にトラックへ吊るし上げられ積み上げられる。ほたてがトラックいっぱいになると、トラックスケールと呼ばれる車ごと計量する施設に移動し、重さを量り荷揚げ完了だ。それを終えたトラックはそのまま各出荷先へ向かう。
また、一部のほたてはそのまま港に隣接する加工場へ運ばれ、鮮度抜群の冷凍貝柱や干し貝柱へ加工される。特に岸壁すぐに隣接されている冷凍貝柱の加工場は水揚げ後最短での処理速度で冷凍貝柱として製品になるというスピーディーさだ。ここはEUのHACCP(ハサップ:危害発生防止を継続的に監視・記録する衛生管理手法)認証を受け、ヨーロッパなど海外への輸出にも対応していて、猿払のほたては国内はもとより海外でも高評価を得ている。しかも宇宙食としても利用された実績があり、実に壮大なスケールである。
しかし、安定した水揚げ量、そして高品質のほたて漁、それも世界が相手ではあるが、現場、特に加工の現場では人手不足の問題があり、それをどうやって解決していくかがこれからの課題のひとつらしい。
加工場等での人手不足という悩みはあるが、オホーツク海最北には日本一、そして世界、また宇宙でも利用されているほたてを漁獲・加工していることを誇りに活躍する漁師さん、そして漁業従事者の方々の笑顔があった。

















