
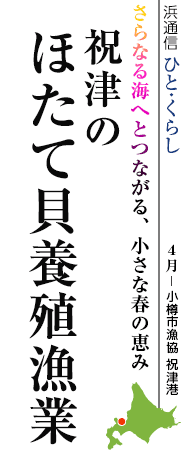
小樽産のほたて?と思う人も少なくないかもしれない。小樽祝津地区では昭和後半からホタテ貝の養殖漁業に取り組み、稚貝の出荷が行われているのだ。今では他の地域からも視察が来るほどの人気。稚貝は漁協を通してオホーツクなどの別の海で育てられ、手のひらサイズの大きなほたてとして市場に出荷される。私たちがスーパーで見ているほたての元をたどると、小樽産かもしれないと漁師さんが教えてくれた。
ほたて貝の養殖は春の採苗や、夏と秋の手入れ、成貝の出荷など作業は通年。祝津では7隻の漁師さんが専業でほたて貝の養殖に取り組んでいる。稚貝が出荷されるのは、4月から5月にかけての春の時期。去年の春に採苗した種が、約1年かけて3~4センチの稚貝となり出荷シーズンを迎え祝津港は賑わっていた。
稚貝の出荷は驚くほど早朝だ。午前3時半、真っ暗な海に向かって7隻の漁船が出航して行く。養殖場には200メートルのロープに30センチ間隔で下げられた丸かごが縦に20段ほど連なっている。水深約40メートルの海底につかないよう調整されているのはほたての天敵ヒトデに食べられないため。ロープに付いている丸い浮き玉を確認しながら調整をしているのだ。
もうひとつ、ほたてにとっての天敵は乾燥。船の上に揚げた後すぐに水をかけながら鮮度を保ち、港へと運ばれていく。港についてからも常に乾燥させないように、水をかけながらの作業が続く。「せーーの!」の大きな掛け声で連なった丸かごを作業台へのせ、稚貝を作業台へ流し込み洗浄。25キロごとのコンテナへ詰めて、たっぷりと水を含んだスポンジで蓋をして、トラックに積まれていく。海から水揚げをしてから約1時間後にはトラックに積み込まれているのは、その日のうちに目的地まで運ぶため。鮮度を最優先しているからこその、スピード感ある作業。
買い手のニーズによって、出荷形態が様々なほたて貝の養殖。希望通りの出荷ができるからこそ、祝津のほたて稚貝は人気があり、生産分は全て予約で埋まっている。一般の人にはあまり目に触れないかもしれないが、知る人ぞ知る隠れた人気ブランドだ。















