
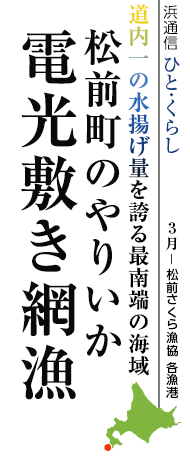
春まだ遠い2月の夜。北海道最南端の町、松前町の沖に煌々と輝く漁火。やりいかの漁をする船のものだ。その明かりは町までをも明るく照らすほど。本まぐろで有名な松前町はいか、とくにやりいかも重要な海産物で、その水揚げ量は北海道一である。
やりいかはまいかと違い大きな移動をしないらしく、普段は近海の深場を主な生息域とし、産卵時期になると卵を産み付ける岩場のある岸際まで接岸してくる。その浅場に集まってきたやりいかを集魚灯で寄せ、網ですくい漁獲するのが『電光敷き網漁』だ。
ここ松前では80年代半ば以降やりいかが産卵しやすいようにと人工礁を積極的に沿岸に投入し、やりいかはそれを利用して産卵するようになり、漁獲量も高水準を継続できるようになった。この辺りのやりいかの産卵期は1月から4月にかけて。最盛期は3月の上旬頃という。松前のやりいかの漁場は、松前小島周辺と松前町の前浜が主となっている。海況が良いと小島周辺まで向かい、波が高いと前浜で漁をする。漁期は2月から5月までだが、ピークは産卵の最盛期に比例し、3月上旬頃とのこと。
2月に入って漁期になっても時化が続いてほぼ一月ほど出船出来ない日が続いたが、月末には出船でき、やりいかの水揚げ量も例年以上の豊漁に港も沸いた。3月上旬、時化は相変わらず続いているが、半日ほど海況がいくらか落ち着くタイミングがあった。すかさずそれに合わせて出漁が決まる。ただし、沖は風が強く小島は不可で前浜での漁となる。
午後4時半、各港から漁船が一艘一艘順番に出航していく。実は出船、漁場の確保には各船に順番が割り当てられていて、漁師さん方はそれをしっかりと守って順番に出船していく。漁場は目の前。漁師さん方は順番にそれぞれの漁場を決めていく。漁場を決めると、まず漁船の前と後ろにアンカーを打ち船を固定する。そして船から前後左右に伸びる4本の桁に網が繋がれ漁船の腹の下に沈めてセットする。このままいかが寄ってくるのを待ち、集まったところを網を寄せて漁獲するわけだが、朝方4時の寄港までこの作業が続けられる。やりいかは基本的に活で出荷するので、漁獲されたいかたちは漁船の腹のイケスに貯められる。
朝4時前。気温マイナス5度。戻ってくる船に合わせて港の岸壁では陸での作業を担うおかまりさん方が荷揚げの準備に忙しい。活での出荷用にトラックも待機。船が戻ってくると一気に荷揚げが始まる。漁船の腹のイケスから次々といかたちが掬い上げられ、サイズで活用と発泡詰め用に分けられる。大きないかは活用で、計量されトラックに運ばれる。同時に氷が敷き詰められた発泡にいかが並べられていく。やりいかは潮やスミを吐きまくるので漁師さんや計量する組合員さん方やおかまりさん方も頭から全身スミだらけになりながら迅速に作業が進められる。食卓に並ぶ新鮮で美味な透明感が際立つやりいかの刺身は、寒風の中、全身スミだらけになりながら作業する方々のおかげだと実感。
春待ち遠しい北海道の最南端の港には、美味しくやりいかを食してもらいたいとの思いで作業する漁業関係者の方々がいる。

















