
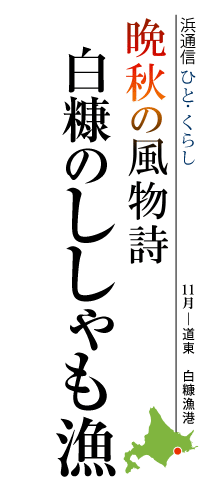
ししゃもは、世界でも北海道南部の太平洋沿岸、水深約120m以下の浅い水域にしか生息していない希少な魚だ。毎年10月下旬から11月下旬にかけて特定の河川を遡上し、川底で産卵。川底で厳冬期を乗り越えた卵は、増水期の春に孵化し、8~9㎜ほどの稚魚となって海へ流れ、やがて餌の豊富な沿岸域で大きく成長してゆく。
道東・白糠町は、そんなししゃもの故郷である茶路川と庶路川、2本の河川が太平洋に注ぎ込む、数少ない好漁場の一つ。白糠漁港を訪れたのは、ししゃも漁が始まったばかりの11月初旬。帰港予定の午後2時前に訪れると、漁港は静まり返っていた…。聞けば、この日は残念ながら時化で休漁とのこと。漁は、毎年10月下旬から約1か月にわたって行われ、10月25日の操業初日には、4.6トンの水揚げがあったものの、それ以降はまだ2日しか操業できていないそうだ。資源保護のため、現在は、小さな未成魚がかかりにくい「こぎ網漁」というコンパクトな漁法で、1シーズンの漁獲量の上限は236トン。また、操業日も21日間までに制限しているので、漁期でも毎日操業するわけではない。天候や海の状況を見極め、「ここぞ!」というベストな日を待ち構え、32隻が一斉に漁場を目指すという。
ししゃも漁の朝は早い――。まだ明けきらない朝4~5時頃に出港し、日の出と共に漁がスタート。昼2時過ぎに帰港すると、スタッフ総出の仕分け作業が始まる。ししゃも以外に、はたはたやこまい、きゅうりなどさまざまな魚が同じ網にかかるからだ。作業が細かいうえに、鮮度が命なので時間との闘いでもある。繊細なししゃもの味わいは、海での資源保護に加え、こうした水揚げ後の手仕事にも守られているのだ。
穏やかな漁港を後に白糠市街を歩くと、あちこちではためく “ししゃも”ののぼりと出合う。鮮魚店の軒先には地元で“すだれ干し”と呼ばれる生干しのししゃもが、寒風に揺られ、ずらりと並んでいた。みやげに買い求め、さっそく晩酌の主役として味わってみる。脂の乗った雄の身はふっくらと甘く繊細な味わいで、雌はプチプチっとした卵の食感がたまらない!“本物”の味と出合った嬉しさに、いつもより盃を重ねてしまった…。















