
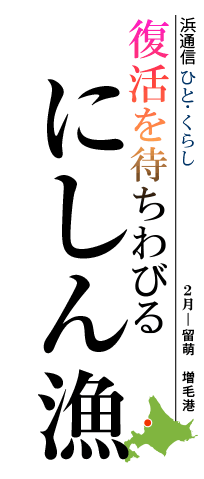
札幌から車で約2時間。日本海岸沿いの231号線を北上すると街並みに変化がみえてくる。明治時代ににしん漁で栄えた増毛町では、今でも古い木造建築が多く残っているのだ。歴史ある建物を通り抜けると見えてくる増毛港。
1月の下旬、漁師さんの仕事は船周辺の除雪から始まる。午前7時ごろ海が明るくなるのを待ち出港するにしん漁は、刺し網漁といって魚が通過する場所を遮断するように網を張り、その網目ににしんの頭部をひっかけるのが特徴。昨日の昼に仕掛けた網には、目印になるボンデン(浮標)をつけている。旗の種類や色によって誰の網かが分かるようになっているのだ。その日、網にかかったにしんは大きくてまるでマスの様!船上のドラムに巻き上げられて網ごと籠に入れられていく。
今日が今年最初のヒットだ!!と漁師の平館さんはニッコリ。にしん漁の解禁日1/15から、どの船もまだまとまった水揚げがなかったという。今日の漁の様子を知った他の漁師さんたちが、次々と網を仕掛けるため船を出し始めた。増毛ではにしんの群れがとどまるのは2日ほどしかないので、また別の群れが来るのを待たなくてはいけないからだという。平館さんの船が網を引き揚げ港に戻ると、すぐに出面(でめん)さんと呼ばれる陸仕事担当の女性たちの手で、網からにしんが外され雄と雌に分けられて出荷されていく。水揚げされたにしんは脂がのっていて、数の子になる卵は黄色いダイアと呼ばれるほどの高級品。ウロコが朝日に反射して七色に光るにしん漁は1月から3月までが全盛期となり、かつてのようなにしん大漁の復活に期待が高まっている。
他にも今の季節は甘えび、かれい、たこ、たら、かじかなどが水揚げされる増毛港。きっと暑寒別岳が作り出すミネラル豊富の水が影響して水産資源に恵まれているのだろう。















