
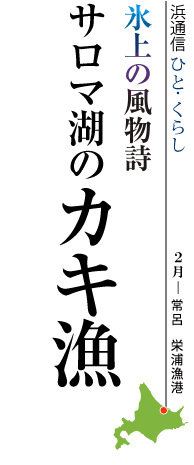
サロマ湖といえばホタテをイメージする人が多いかもしれない。マイナス10度を下回るサロマ湖の冬。湖上が氷で覆われて船の出港が出来なくなるため、ホタテ漁から船を使わない養殖のカキ漁へと切り替わるのだ。サロマ湖東南に位置する常呂町の栄浦漁港を訪れたのは2月上旬、寒さと共にカキ漁がピークを迎えている。
凍てつくような海風がピリピリと肌をさし、厚い氷に積もった雪はサロマ湖に真っ白な風景を作りだした。まさに「しばれる」なかでの氷上のカキ漁だ。
常呂地区でカキの養殖をしている漁師さんは75名。各自の養殖場で、厚さ20センチほどの湖上の氷を突き割り、ロープについたカキを手作業で引き揚げている。一本のロープにはカキの塊がゴロゴロとつき、水を含んだ重さは約20キロ。防水カッパを着ているが引き揚げる時にかかる湖水は、体を芯から凍りつけそうだ。ロープを引き揚げながら「今日のカキはつきがいいな」と笑顔の漁師さん。寒さよりもカキの成長が気になるのだろう。あっという間に大きなネットいっぱいのカキが積み上げられていた。
漁師さんが教えてくれたカキの生存率は約60パーセント。春に宮城から種ガキを買い、ホタテの貝殻に付着させロープに吊るして沖で成長させる。湖に氷が張る前に湾の中に移動させるが、波でロープから振り落とされたり、海の環境によって成長できずに死んでしまう。養殖ではあるが自然の影響は大きいのだろう。流氷によって運ばれてきたプランクトンたっぷりの海水と、佐呂間別川の淡水が混ざり合うサロマ湖は恵まれた環境だ。
「1年牡蠣だから小ぶりだけど美味しいよ」漁師さんがくれたのは、手のひらにすっぽり収まるサイズ。旨みと甘みがギュッと濃縮されていて美味しさはもちろんだが、クセがないことに驚かされる。栄浦漁港では成長過程によって養殖場所を移動している。栄養分の多いところや雑物の少ない場所へのこだわりによって、カキが苦手な人でも食べることができると好評だ。
サロマ湖のカキ漁は氷が解け始める3月上旬まで。冬の味覚であるサロマ湖産のカキは、寒さがピークをむかえる今だからこそしっかりと味わいたい。















