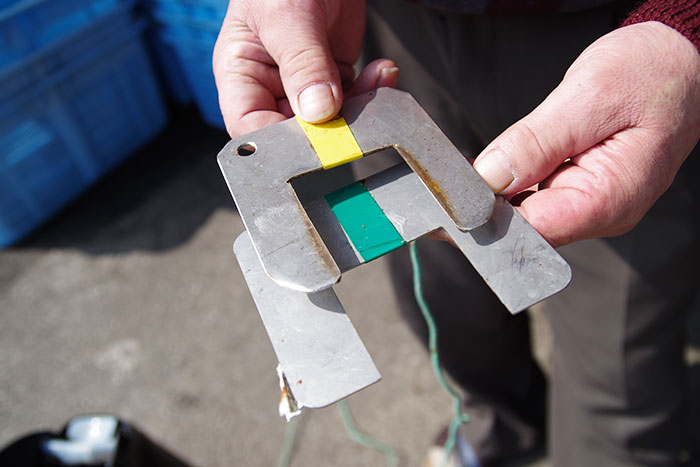流氷の影響で休漁と聞きがっかりしていると、「そんな都合よく漁はないよ!」と漁師さんのひとこと。ウニ漁は漁場につくと箱メガネで海中をのぞき、足で櫂[カイ]を操りながらウニを探す。小さい船なので少しでも時化ていたり、雨の後で海が濁ったりしていると出漁はしない。まして1月から始まる漁期は流氷とのにらめっこ。風で流氷が沖に流される合間をぬって漁に出ていく。
今年出漁したのは1月から3月末までで、たったの27日。これでも例年に比べると多い方だという。漁のない日が一週間続くこともある。「限られた期間だからこそ、いかにぎっしりと実が詰まっていて美味しいウニをとるかが大切」20年以上の経験をもつベテラン漁師四ツ屋さんが教えてくれた。狙いは3年草の昆布を食べているウニ。殻の外からは実入りは分からないが、ウニは食べているものがそのまま実に影響するので、育っている場所の昆布をみて判断するのだ。3年草の昆布を食べているウニの殻を開くと、トロッとした昆布のねばりがそのまま実となり、雑味がなく濃厚な甘さがあるという。四ツ屋さんのウニは味や形などの品質がよいと、仲買人さんたちの評価は高い。
そんな四ツ屋さんのおすすめは”ピンク”と呼ばれるウニ。見せてくれたのは色分けされ、きれいに並べられた折だった。鮮やかな黄色からオレンジがかった赤っぽいエゾバフンウニが折ごとのグラデーションとなり芸術品のように美しく並べられている。ウニを大きく区別すると黄色系と赤系。黄色系はとろけるような食感で、赤系は濃厚な味わい。そのなかでも色の濃さによって分けられているのだ。赤系のピンクは濃厚さとやさしい食感を持ち合わせた、赤と黄の好いとこ取りなのだろう。実際に市場で高値が付くのもピンクのウニ。地元のお寿司屋さんでカウンターに並んでいた折もそうだ。なるほどと納得しながら食べたウニは、濃厚で口の中でトロッととけていった。