
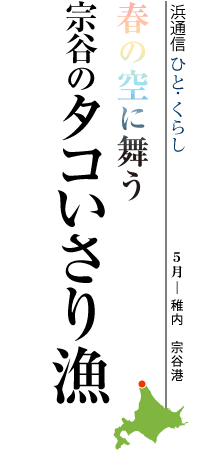
タコは鮮度が命。活きたまま港に運ぶため、船には必ず水槽が付いている。張り付くと剥がすのにかなり厄介なタコの吸盤。元気がいいタコだからこそ、吸盤が張りつかないように気をつけて船から放り投げているそうだ。なかには水槽の屋根にベッタリと張り付いてしまい、どうやっても取れないと苦笑いしている漁師さんもいた。宗谷港は4月から始まったタコいさり漁で漁船が行きかい、賑わいを見せている。
タコいさり漁とは、熊手のような仕掛けの「いさり」を浮きとなる樽につなぎ海に流してゆく。タコがいさりにかかり、グッと沈んだ浮きを合図に引き揚げる方法だ。潮の流れと漁場をきちんと把握したうえで仕掛けを流さなくてはいけないため、漁師さんの経験と技術が重要となる。タコ漁の大きな決まりはたった2つ。最終帰港時間といさりの数が20個まで。出港して3,4時間ほどで戻ってくる船もあれば、夕方ギリギリまで操業している船もある。漁師さんの腕次第なので、水揚げの量はかなりバラバラ。タコ漁の漁師さんは個人プレーヤーなのだ。
夜明けに出港した船が7時ごろから一隻、また一隻と港に戻ってきた。「よっこいしょ」と漁師さんの掛け声が聞こえてきそうな、大きなタコが次から次へと飛んでくる。2.5kg以下だと海に戻さなくてはいけないので、どのタコもゴロッと大きい。「宗谷の海は流れが速いので、ここで獲れるタコは身が引き締まって活きがいいぞ」と漁師さんのお墨付き。そんな話を聞いてふと水槽を見てみると、吸盤を使いニョロニョロと逃げだしたタコを発見。脱走するタコはよくいるようだ。タコってこんなに動くのだと感心していると、漁師さんが獲りたてのタコを鉄板で焼いて差し出してくれた。塩こしょうでサッと味付けされたタコは、驚くほど甘くプリップリの歯ごたえがありながらも、簡単に噛み切れる柔らかさ。活きたまま水揚げされたからこその食感と味わいだった。














