
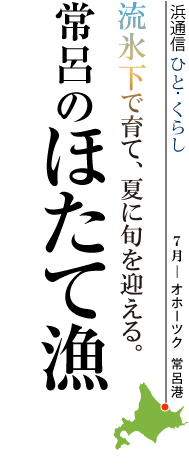
真冬にオホーツク海を埋め尽くす大きな流氷。厚い蓋となって海中のほたてを時化から守りながら、運んできたプランクトンで栄養たっぷりの海へと変えていく。そんな海の中、寒さで身がひきしまりながらも大きく成長していくオホーツクのほたて。
お刺身で食べるのを勧められ、まずはそのまま一口。驚くほどの濃厚な味わいだ! ほたては夏になるとうまみを蓄積していくのだ。冬の寒さでつくられた引き締まったプリプリの食感と、夏の旨みがギュッと詰まったほたて。冬と夏の良いところを味わえるからこそ、ほたての旬は夏なのだ。そのほたての資源を絶やさないために、常呂の漁師さんには果たさなくてはいけない義務がある。それが毎年1人200万粒の稚貝放流だ。サロマ湖で稚貝を約1年かけて4cmほどに育て、その後オホーツク海へ。漁場を4つの海区に分けて1年ずつ放流し、じっくり育て4年目に漁獲している。なによりも「育てる漁業」を大切にしているのだ。
ほたて漁は昔から変わらず「八尺」と呼ばれる大きな網を使っている。網の先に熊手のような爪が付いた「八尺」を使い、海底からほたてを掘り起こしていく桁網引き漁法。大きな「八尺」をみると豪快な作業だと想像できる。
常呂港を訪れてまず目に留まるのは、大きな網に入ったほたてがクレーンで運ばれている風景だ。帰港した漁船には甲板にあふれるほど積み重なった大量のほたてたち。ザザザザッとほたて同士がぶつかり合い音を立てながら、見上げるほど高く持ち上げられ、トラックの荷台へと運びこまれている。何度も繰り返しているクレーン作業は迫力があり、釘づけになってしまうほどだ。一体ほたて何個分だろうと思い尋ねてみると、「漁船一隻で約25トンの水揚げだな。クレーンで持ち上げているのは一回だいたい1~2トンぐらいかな。」とダイナミックな回答。常呂ではほたて漁船13隻で1日なんと約330トンのほたてを水揚げしている。1キロで約5~6個のほたてだから、330トンで約200万個?!! とにかくすごい量だ!
豪快なほたて漁に驚きながら、豊富な資源は稚貝放流を大切にしている漁師さんたちの「育てる漁業」があるからだと感じさせられた。豊かな海と上手に共存するための努力をし続けているのだ。















