
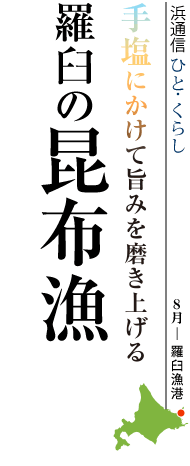
食のプロが好んで使うことで知られる羅臼昆布。高価なイメージがばかりが先行してしまうが、それに見合う、いや、想像を覆すほどに手間ひまをかけて作られていることはあまり知られていない。
「われわれは手間を売っているようなものだよ。乾かした昆布をわざわざ湿らせたりするんだからね」。そう話すのは、羅臼天然昆布部会長の井田一昭さんだ。
「羅臼昆布」と称されるものは、エナガオニコンブという種類。30を超える河川の流入、年間を通して低い海水温、沖合いで湧く海洋深層水のミネラル・・・知床の環境に育まれた天然昆布は、ヒレ(端の部分)までピンっと張りがあり、健康そのものといった雰囲気だ。その高い品質をさらに磨き上げるのが、漁師さんが手がける40もの工程だ。
取材は、昆布漁が最盛期を迎える7月下旬。朝6時、羅臼の前浜に集まった漁船が、白旗の合図でいっせいに漁を始める。箱メガネで海中の様子を見定めながら昆布棹を操り、2年ものの昆布に狙いを定め、ねじ切るように引き上げる。11時、漁の終了時刻とともに、今日の収穫を満載した船は作業場へと向かう。
浜に揚げられた昆布は水洗いされ、干場で天日干しされる。これを繰り返すこと3日。これで製品になるかと思いきや、羅臼昆布を磨き上げる時間はここから。干しが終わった昆布を、日が落ちてから再び浜に並べるのだ。これは、次の加工をしやすくするために夜露で湿らせる作業。頃合いを見計らって、夜のうちに番屋に取り込む。
ほどよく湿った昆布を一枚一枚、シワを伸ばしながら玉状に巻いていく。それを一晩寝かせ、「あん蒸」へ。これは伸ばして積み上げた昆布をシートでくるみ、重しをかけて1~2晩熟成させる作業。旨みを香りを凝縮させる重要な工程だ。
この後、さらに天日に当てて、ようやく製品となる準備ができる。ヒレを切り落とし、等級別に仕分けて梱包したものが、羅臼漁協の厳しい製品検査を受けて、全国へ出荷される。
天然昆布漁を始めて40年超のキャリアを持つ井田さんは言う。「作り方は昔からずっと変わらないから、特別なことをしている意識はないよ。手間をかけた分、旨くなるからね」。羅臼のブランドを牽引している自信と誇りが、その表情には表れていた。
羅臼昆布で取った出汁は、味も香りも濃厚で力強い。それは、羅臼の海と気候、そして漁師さんたちの想いの結晶なのだ。















