
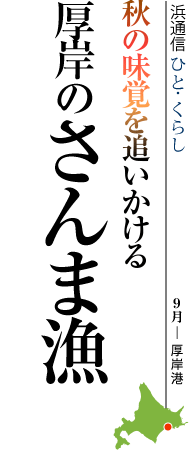
初秋をむかえて本格的に始まったさんま漁。実はこの季節の漁場は厚岸沖ではない。群れは厚岸からまだまだ遠い北東側の根室東海域にあり、これから寒くなるにつれて徐々に南下してくる。群れがいる漁場までは片道約36時間。一晩かけて漁を行い、再び港に戻ってくるまでに、5日もかかるのだ。漁師さんにとって揺れる波の上での生活が続く。
長距離の移動後、漁場に着いてからが漁師さんにとっていよいよ本番。さんま漁は「棒受け網漁業」といって真っ暗な夜間一晩中行われる。まずは船の右側にだけライトをつけて群れをおびき寄せ、光に近寄ってきたところで灯りを消す。そして、すかさず逆の左側を明るくし大きな網へとおびき寄せる。光に群がる習性を利用して、網に誘導する仕組みだ。船に揚げたさんまは砕いた氷と一緒にして船底のタンクへ。用意された氷約10トンによって鮮度を落とすことはない。鮮度を保ちつつ、再び36時間かけて港へと戻ってくるのだ。
夜の厚岸港には、漁を終えた船が帰港していた。数時間後に始まる早朝の水揚げまでの時間が、漁師さんにとってほんのわずかな休息時間となる。朝焼けでうっすらと明るくなると、「ピーーーッ!」と笛が鳴り響いた。水揚げが始まった合図だ。朝7時からのセリ直前に船から水揚げすることで、活きのいいさんまを出荷する。8名の漁師さんが一斉に動き出す。タモと呼ばれる先に網のついた長い棒を使い、船底からさんまをすくい揚げる。一回の量はなんと100キロ以上。船のクレーンで引き揚げた網からは解けた氷水がザザザッとすり抜け、陸で待つ1tコンテナへとさんまを運んでいく。ピッタリと息の合った呼吸で、約30tもの水揚げが1時間もかからず終了した。漁師さんの手際の良さと大量の氷で冷やされていたことで、鮮度はとても良さそうだ。そして驚くことに、水揚が終わると燃料と氷を補充してすぐに出港。秋の味覚の王様と呼ばれるさんまを全国のお客様に届けるために、今日も漁師さんは休む時間を惜しんで次の漁へとむかう。















