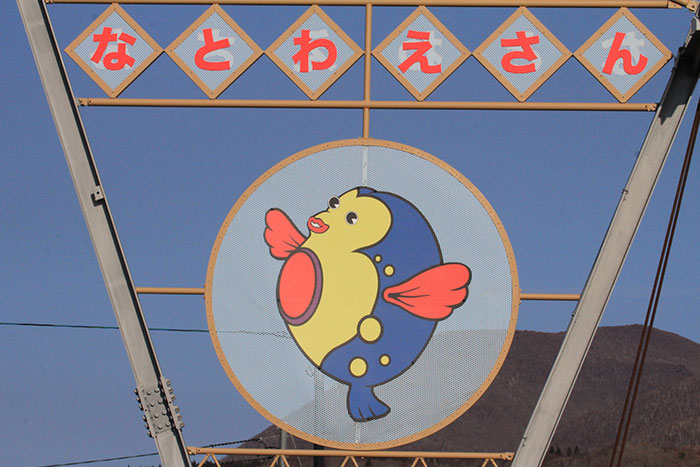駒ヶ岳や恵山といった火山が並ぶ渡島半島南東端・亀田半島の沿岸は、砂浜が少なく、多くが岩場の磯で構成されているが、この磯に時化早い12月から4月にかけてごっこは産卵のために接岸してくる。普段は沖合の中層から表層にかけて生息しているごっこだが、産卵期になると10mもないような浅い沿岸に集まり産卵する習性をもっているのだ。
北海道内でも降雪・積雪量の少ないエリアではあるが、だからといって暖かいはずもなく、舟を出す早朝6時の気温はマイナス。真水だと全てが凍ってしまう世界だ。
港前の倉庫で支度をし、暖をとっていた漁師さんは凍てつく中、斜路から磯舟をおろす。そしてまだ暗い中、安全を確かめながら港の目前のエリアに向かった。水深が6~9mラインにごっこ刺し網(3枚網)を二日前に仕掛けておいたのを上げにいく。ゆっくり網を上げて行くと、褐色のゴロッとした魚影がひとつ、ふたつ、みっつ……かかっている。それがごっこだ。ごっこがかかっている網を上げ終わると、港へ戻る。舟を陸に上げて網を軽トラに移し、倉庫へそれを運ぶ。倉庫では網を広げてごっこを1尾ずつ丁寧に外していく。網から外され、オスメス分けられて魚箱に入れられたごっこたち、中にはクワッと鳴いたりするものがいたり、その容姿もこわいものからかわいいものまでさまざまなのが面白い。どうやら産卵期になると歯が鋭くなるようで、それがちらっと見え隠れする個体がこわく感じるのかも知れない。そんなごっこを漁師さん方は、「みんなめんこいよ(かわいいよ)、ほら !」と微笑みながら並べていく。魚箱に並べられたごっこは、この後すぐに市場へ運ばれ出荷される。
ごっこ漁は網を入れて海況を観ながら2日目以降に上げるのが良いと漁師さんは言う。どうもごっこはメスにオスが複数寄り集まって行く習性をもっているようで、網を入れて1日ですぐに上げてしまうと漁獲量が少なくなるらしい。メスが網に入ると、それを目指してオスが集まってくるので、それを期待して二日待つということだ。また、ごっこはメスが重宝される。ごっこ汁などを口にするとその卵がたいへん美味であるからだ。メスは岩場を好むようで、海底が砂場になるとオスが多くなるという。漁師さん方はこういったごっこの習性を熟知し、それを利用して漁をしている。
厳寒の時期に身体を芯から温めてくれるごっこ汁。一度口にすると忘れられない上品な味をもつごっこ……恵山の麓の磯にはたくさんの福を与えてくれるごっこと、どこか暖かくやさしい漁師さんたちがいた。