
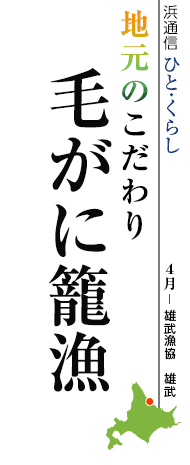
堅い甲羅に鋭い2本のハサミ。全体を毛に覆われたその見た目からは想像もつかないが、何度も脱皮を繰り返して成長している毛がに。地元で毛がにといえば2種類。流氷が去った海明けの春のかにを「堅(かた)がに」、脱皮後の柔らかい夏のかにを「若(わか)がに」と呼び分けている。甲羅が堅く、身とミソがギッシリとつまっているのが堅がにだ。寒さが残るオホーツク海でとれた堅がにのミソはほんのりとした苦味に濃厚なクリーミーさが絶品だ。4月下旬に行われる『毛がに祭り』に向けて活気づく雄武。たくさんの人たちを遠方からも集める毛がにの魅力は、漁師さんのこだわりによるものだと地元の人たちは口を揃えて言う。
雄武漁港の毛がに漁船10隻は、夜明けと共に出港しはじめる。前日に仕掛けた籠を引き上げるとすぐに、船上で漁師さんによってきびしい選別があるのだ。ここが漁師さんの腕のみせどころ。毛がに漁は資源管理のため、甲羅8センチ以上の雄しか獲ってはいけないという規則があるが、それは当たりまえ。雄武ではさらに、甲羅の色や堅さの微妙な違いで、味や身詰まりをチェックする。手に取った感覚で美味しいか美味しくないかを判断し、商品としての見極めを瞬時に行っている。素人では区別のつかない違いも、漁師さんにかかればその差は歴然。納得のいかない毛ガニは躊躇なく海に戻していくのだ。一般的に商品になるものも、雄武では認めないことが多いそうだ。これは規則というより、美味しい毛がにだけを出荷したいという漁師さんのこだわりだ。
そんな想いは毛がにを茹でる加工場にも引き継がれていた。加工場に届く毛がにはどれも身詰まりがよく、綺麗な毛がにばかり。加工場の選別でロスになるものはほとんどない。漁師さんのこだわりを目の当たりにするからこそ、加工場でも毛がにひとつひとつを丁寧に扱わなくてはいけないと感じているそうだ。漁師さんの妥協を許さない姿勢が雄武地域全体へと広がり、ブランドとしての価値を上げているのだ。















