
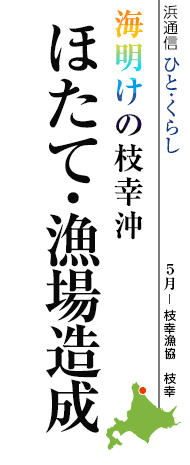
本格的な春まであとわずか。浜風にも温もりを感じられるようになる頃、枝幸の沖ではほたての漁場造成の時期を迎える。
ほたて漁業は、大きく次のふたつに分けられる。「地撒き式」と「垂下式」。ここ、枝幸漁協を含めたオホーツク海側、及び根室海峡地区では地撒き式で行われている。
地撒き式とは、ふ化して1年育てた稚貝を海に放し、海底で数年成長させ、それを漁獲するという方法。枝幸沖では「4輪採制」という、漁場を4つに区切り、1年毎に区画をかえて放流する(4年間成長させて収穫する)方法をとっている。そして、ここで重要なのが、「漁場造成」だ。
漁場造成とは、流氷が去り、海明けとなる3月初旬から5月末ころまで、4年後の資源となる稚貝を撒くための漁場(区画)内のヒトデ等外敵駆除と底質の改良を行い、そこに稚貝を撒く(放流する)というもの。つまり、畑で例えると、土を耕し、種を撒くことと同じと考えて良い。それが終わると、4年前に稚貝を放流した漁場で大きく育ったほたての漁獲が開始されることになる(6月~11月)。それを「本操業」という。
本操業は、4年間自然のまま海底(水深30~60m)で成長させたほたてを漁獲するため、通称八尺(熊手を大きくしたものに袋網をつけたもの)という漁具で海底を曵いて漁獲する。
枝幸の漁場の特徴は、他の地区と比較して底質が細砂・砂泥質のところが多く、ほたてが砂に潜り込んでいるために漁獲しづらい状況となっていること。そのため、外敵を駆除する専業船の船頭さん方は、各漁場毎に曵時間・曵方法・漁具の改良等を日々研究しながら本操業を行っている。
枝幸のほたては旨味が強くとても美味しいと大評判だが、そこには流氷の恩恵と、同時に豊かな森林から生まれる栄養が川の流れによって注がれ、さらに栄養豊富な海になりほたても豊潤に成長する図式がある。北海道では、全道の漁協女性部を中心に山の緑を育てる「100年かけて100年前の森林にもどす」植樹活動に取り組んでいる。ここ枝幸漁協も例外ではなく、毎年熱心に植樹に取り組んでいる。
流氷と山の木々の恩恵を受けたオホーツク枝幸では、たっぷり栄養を蓄えたプリプリのほたてが、最も甘み・旨み共に強くなる初夏を迎える。

















