
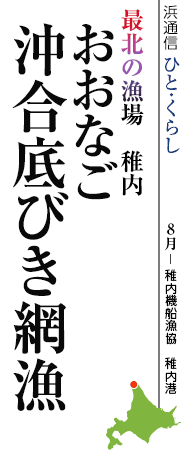
「おおなご」は、稚内では昔から燻製として食しており、水揚量日本一を誇る。本州ではイカナゴと呼ばれ、ちりめんや佃煮などに調理される2~3センチほどの小さな魚。ここでは25センチほどまで大きく育ち、外見は小ぶりのサンマのよう。たっぷりと脂がのっているが、淡泊な白身魚のような食味をもつ複雑な味わいがおおなごの特徴といわれている。
160トン漁船の栄宝丸はおおなご漁専門のオッタートロール船。早朝に出港した船が港に戻ったのは夕方の4時を過ぎていた。水深50~70mの漁場で大きな網をまわしながら魚を集める沖合底びき網漁は、たくさんのおおなごを集めることができる。クレーンを使い船からトラックへと豪快に移していく水揚げ。カモメにとって脂がのったおおなごは格好のねらい目となるため、トラックの荷台はつねにシートを覆う慎重な扱いだ。その日の水揚げ6トン分をのせたトラックはすぐに加工場へ向かい、鮮度を保つための冷凍処理が始まる。パンと呼ばれる箱へ15kgずつ入れて、一晩マイナス30℃の急速冷凍室へ。全て冷凍してからの出荷となる。
おおなごを本格的に水揚げしているのは稚内のみ。身がやわらかくて鮮度落ちが早く、取扱いがとても難しいため、ほとんどが蓄養マグロやハマチの餌として出荷されている。そんな中、稚内の昔から食べられている味として食材として残したいという声があり4年前から稚内市でブランド化への動きがあった。しかし他にも、ほっけや、すけそうだら、かれいなど美味しくて魅力的な海の食材が多いため、扱いの難しいおおなごまで手がまわりきらないのが悩み。とはいえ地元で昔から食べている食材。全国に出荷されなくても稚内にあり続けてほしい味だと思い、地元水産会社では加工品として「おおなご」の味を残す商品化を続けている。
昆布〆や魚醤などが稚内市内の数か所で販売され、空港のレストランでは「おおなごの蒲焼き丼」を味わえる。おおなごが大きく育つ稚内ならではの名物丼なのだろう。稚内の守り続けたい味がそこにあった。















