
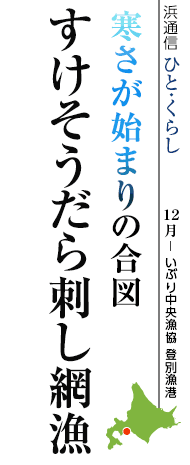
「寒くならないと仕事にならない!」白い息を吐きながら漁師さんはいう。10月から始まった漁だが、今年は秋のポカポカ陽気がながく、本格的な寒さが訪れたのは12月に入ってからだった。すけとうだらが好む水温はなんと3℃前後。太陽の光が届かない水深300mほどの冬の海底に群れをなしている。寒さと一緒に現れたすけとうだらは、大きさも味も最高のとなり、まさしく旬をむかえていた。
本格的な寒さを待ちわびていた登別漁港では、34隻の漁船が夜中から出港していた。船が戻ったのは早朝3時。休む間もなく手作業で1匹ずつ網から外す「陸(おか)まわり」の作業が始まる。屋根も風よけもない港で、冬の海風にあたりながらの作業は、心が折れそうになるほどの寒さを感じる。そんな中でも漁師さんが笑顔だったのは、その日は一隻で10トンの水揚げがあったからだ。水揚げの多さが寒さを一気に吹き飛ばしてくれるのだろう。
しかし10トンのすけとうだらを網から外し終わったのは、8時をすぎ辺りは明るくなっていた。気温がマイナスになった港での作業は5時間以上だったが、海の水温が下がりはじめた今、やっと今シーズンの手ごたえを感じているようだ。
活気づく港で漁師さんが教えてくれたのは、すけとうだらの価値はメスがもつ卵巣「たらこ」で決まること。その中でも寒さが厳しくなる時期の真子と呼ばれるたらこは、粒がたっぷりと詰まりしっかりとした食感で絶品だという。漁期は10月から3月までだが、毎年船をだすのは2月までと決めているのは、産卵直前となる3月には旬が過ぎて味が落ち始めるから。自主的に漁をやめる、漁師さんたちの品質へのこだわりだ。そんな味への想いが、いぶり中央地域の「虎杖浜のたらこ」としてブランド化され、全国へと出荷されている。
そしてもうひとつのこだわりは、次の世代へ資源を残すことだと言う。「虎杖浜のたらこ」が世間から認められたのは、この漁場の資源を大切にしていた前の世代の漁師さんがいたからこそ。今は漁獲規制や網目の大きさのガイドラインをきめ、次の世代にも資源を残し続けようと取り組んでいる。















