
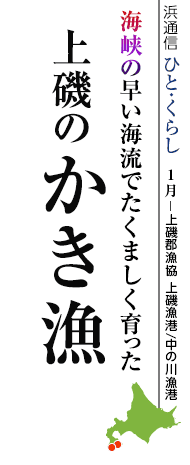
道南は上磯から知内にかけて盛んに養殖されているのが牡蠣だ。昭和50年代初めから始まった養殖事業は、現在では地元の主要な産業となり、その大きく身が締まった牡蠣は栄養に富み、たいへん美味である。
暖冬とはいえ、指先の感覚が麻痺するほど寒い早朝5時すぎ、まだ真っ暗な港には出船の準備をする漁師さんの姿が。
真っ白な息を吐きながら準備を整え、漁師さんたちは沖合で養殖している牡蠣を引き上げに向かうため岸壁を後にする。
上磯から知内にかけての牡蠣は他に類をみない環境の下で養殖されている。外海養殖と称されるその方法は、通常の湾内や内海で行われるものとは違い、津軽海峡の早い海流の中で育成させるため身の締まりが強いという特徴がある。
海中からクレーンで引き上げた牡蠣を船上いっぱい山積みにして船は戻って来た。
そして、休む間もなく船上で牡蠣の選別作業が始まった。冷たい風が雪を伴って吹き付ける中でのその作業は大変だ。漁師さんたちの身体もみるみるうちに風が当たる側が雪で白くなっていく。
作業は、牡蠣以外のイガイ等もびっしりとついているので、まずはそれを取り除きながら牡蠣をロープから外すことから始まり、外した牡蠣を殻の形状とサイズで3つに分ける。
大きく形の綺麗なものは殻付き販売用。殻の形状が複雑なものは加工用(剥き身)。それとサイズが小さなものはもう一度海中に吊され(籠に入れられて)、春頃に身入りが良くなってから再び引き上げられて出荷される。
剥き身用に選別された牡蠣は加工場へ運ばれ、パートさん方の手によって素早く剥き身にされる。目前に山積みにされた牡蠣をひとつひとつ丁寧に捌いていくその姿は壮観だ。聞くと、剥き身用の牡蠣は形がいびつなものが多いので、それを傷つけずに開くことが大変だとのこと。専用の細長いナイフで丁寧に貝柱を攻めるのがコツのようだ。剥き身は滅菌水に浸されて出荷される。一方、殻付きのまま出荷するものは、殻を綺麗に洗浄し、その後オゾン滅菌し、エアレーション(水中に空気を溶かしこむこと)している海水の生簀にて48時間浸され殺菌してから出荷される。これらひとつひとつの工程から、消費者に対していかに食の安全を考えているかが伺える。
なお、上磯郡漁協上磯支所に隣接している『貝鮮焼・北斗フィッシャリー』にて、出荷されたばかりの新鮮な殻付き牡蠣をお腹いっぱい食すことができる。また、知内町では来る2月21日、日曜日、『第18回しりうち味な合戦冬の陣 カキVSニラまつり』が開催され、知内町中央公民館にてカキとニラの販売、スポーツセンターではカキとニラの創作料理を食せるイベントが行われる。海峡の海流に育まれたぷりっとした歯ごたえの牡蠣を鮮度抜群で食せるのは嬉しい。
道南の上磯の浜には、厳寒の中でも、味はもちろん食の安全という消費者のことを思って徹底した作業を行う漁師さんたちがいた。
上磯の牡蠣の旬はこれからだ。















