
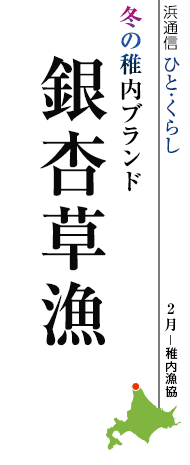
銀杏草といえば天然海藻の高級品。そのほとんどが北海道の日本海側でしか採れず、希少価値が高いのが理由のひとつだ。近年では天候の変化などによって、ますます生産量が減っている。だからこそ価値を知ってもらうためにも稚内では5年前から「稚内ブランド」として銀杏草を認定して、全国に魅力を発信している。寒さがピークとなる2月は旬の季節となり、鮮銀杏草が地元のスーパーに並び始めていた。
地元ではお味噌汁の具として食べることの多い銀杏草。冬になると当たり前のように普段の食卓にならぶが、他地域では希少価値のある高級食材だ。わかめとも、海苔とも違う、強い磯の香りとコリコリの食感。銀杏草を食べると冬を感じるのだと地元の人が教えてくれた。歯応えのある食感で食べるならサッと茹で。じっくりと火を通すと、トロッとしたやわらかな口当たりに変わっていく。好みの食べ方を話している稚内の人たちを見ていると、銀杏草が地元の食材として根付いているのだと感じた。
銀杏草漁は全てが手作業で行われている。漁場となる前浜近くに車を停め、頭まで覆う厚手の特製ウエットスーツを着て漁が始まる。躊躇することなくマイナスの海へと入っていく漁師さん。大きな水中メガネを使って、岩に張り付いた銀杏草を探し、タモですくい上げる作業は長い時で数時間。腰紐とつながっている網に次々と採った銀杏草が溜まっていく。浅瀬とはいえ、胸以上の深さがあるところもあり、足場が悪いのでとても危険な漁だという。漁の様子は見ているだけで凍えそうだが漁師さんが教えてくれたのは予想外の言葉だった「海の中で動くのは力が必要で、漁が終わることには汗をかいているよ。」北の海の漁師さんのたくましい一言だ。とはいえ、マイナス10度を下回ることもある稚内の冬の海。作業をしながら、道具が凍りつくこともある。大型漁船を使うような豪快さはなく地味で根気がいるのが銀杏草漁だが、寒い時期だからこそ美味しい銀杏草を採ってみんなに食べてもらいたいのだと漁師さんは白い息をはいて笑っていた。















