
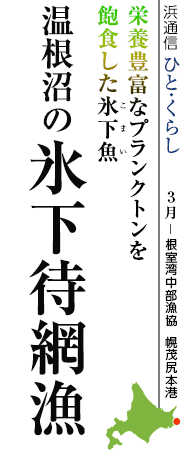
3月ともなると日が長くなり、どこか日差しにも力強さが漲っている。しかし、ここはまだまだ厳しい寒さだ。
北海道の東端は根室半島、その付け根に位置しているのが温根沼だ。沼ではあるが、ここは汽水湖であり、海の魚が豊富な沼である。今年は暖かいとは言うが、2月下旬~3月上旬でも50センチはある分厚い氷に覆われている。ここで正月明けから氷が溶けるまで行われているのが、字のごとく氷の下に専用の小型定置網を張り、2~3日置いて網揚げをする『氷下待網漁』だ。
朝6時、漁師さんたちは漁の準備をして沼の畔へ集まる。そして気温マイナス10度を下回る中、各自スノーモービルで漁場へ向かう。舟で向かうわけではなく、スノーモービルで仕掛けてある網を起こしに向かうのはここ独特の光景だ。その漁場まではモービルでゆっくり走っても5分もかからない。水平線が遥か彼方まで広がるように真っ白な雪原。しかし、ここは沼の上だ。移動するモービルの後ろをオジロワシやオオワシがついてくる。漁師さんが選別し、出荷しない魚を頂戴するためだ。また、シカの群れも氷の上を走り抜けていく。ここは何もかもが違う。ダイナミックな自然の下での漁だ。
漁場へ着くと先ずは専用のマサカリで網が入っいる部分の氷を割り、それを掬う。そして網を支えている綱を緩め、いよいよ網揚げだ。ふたりで息を合わせて丁寧に揚げてくると、袋の部分で銀鱗がピチピチと跳ねている。カゴへあけると、「ちか」や「にしん」に混ざって独特の黄色い体色をしている「氷下魚」や「おおまい」の姿が観られる。「かじか」や「かれい」も入っているが、メインは「氷下魚」。ここの「氷下魚」は特別だ。氷の下にはおびただしい数のプランクトンが湧くようにいて、それを飽食しているので、旨味と香ばしさのレベルが違うというわけだ。
漁師さんたちは数カ所に設置している網をひとつひとつ揚げて、そして設置し直していく。それを繰り返して漁を行い、獲れた魚を番屋へ運び細かな選別をして出荷となる。
水面がほとんど見えない漁である氷下待網漁。チェーンソーで穴を開けて水深2mほどのところに網を仕掛けていくのだが、漁師さんたちは長年の経験と沼を取り巻く環境を観察し、沼の水深の深いところを狙ってきっちりと仕掛けていく。それはワシやシカと同じく自然にしっかりと溶け込んでいる証でもある。
北海道の東端は温根沼には、大自然とそこに生息する生きものたちと共存共栄している心温かく優しい漁師さんたちがいた。

















