
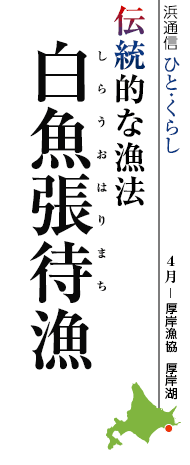
太平洋の海水と別寒辺牛川からの淡水が混じる汽水湖として良質な漁場となっている厚岸湖。湖の氷が解け始める3月下旬、春の風物詩である木の櫓を組んだ白魚の張待(はりまち)漁が始まった。鮮度にこだわる昔ながらの伝統漁法だ。
獲れたての白魚の透明感はすごい! 透きとおった10センチほどの体には、ちいさな銀色の目玉と黒い斑点だけが鮮明にみえて、まるで繊細なガラス細工のよう。見た目だけではなく味も繊細で、料亭の懐石料理につかわれる高級食材だ。死んでしまうと白く濁ってしまうため、厚岸では活きたまま水揚げする張待漁を続けている。
結氷していた湖の氷がとける春を待って始まった張待漁。まずは「建て込み」という1本約10メートルほどの木の杭を海底に打ち込む漁場作りから始まる。1つの漁場を作るのに使う杭はなんと100本! 全て手作業で行うのだから驚きだ。上から見て八の字型に打った杭に櫓を組んで網を固定し、広い入口から先端の網へと白魚を追い込んでいく。狙いは潮入りによって湖に海水が流れ込んで移動してくる白魚たち。潮の流れを計算し、自然をうまく利用した昔ながらの漁法だ。
長く続いている白魚漁だが、数年前に漁獲量が減り1年間休業したことがった。目先の利益を考えるなら、もちろん少しでも獲れたほうがよいが、あえて資源を育てるための休養期間をつくったのだ。その期間、漁師さんの収入はなくなってしまうので当然厳しい状況ではあったが、これからの資源の事を考えての決断だったという。他にも海産資源を守るために昭和62年から行っている植樹がある。森を大切にすることで川が豊かになり海の資源へと影響を与えているのだ。漁業は「獲る」だけではなく、海産資源を次の世代へと引き継ぐために「育てる」ことも大切なのだと厚岸の漁師さんが教えてくれた。















