
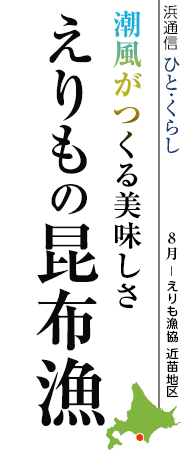
良質な昆布を選んで海の岩場から引き上げる、それがえりも昆布漁の凄さだ。昆布は海の中で光合成を行い成長しているため、日当たりの良い場所で育った昆布は色が深く栄養をたっぷりと蓄えた上級品。8月のえりも近笛地区では、漁師さんの鋭い目利きによって昆布が水揚げされていた。
意外かもしれないが、昆布漁の操業は天候の影響がとても大きい。船が出港できるかどうかは「旗元」と呼ばれるベテラン漁師さんがその日の天候を見て判断する。ただし、他の漁と違い海が穏やかなだけではその日の操業は出来ない。えりもで採れた昆布は天日干しているため、その日1日の天気を予想しなくてはいけないからだ。太陽の光と潮風を浴びてじっくりと自然の中で乾燥することにより、旨味がギュッと凝縮されて風味のある昆布となっている。そのため、7月から9月の漁期で実際に船が出るのは良くて20日間。漁が出来てもしっかりと天日干しをしないと価値が下がってしまうので、旗元の判断はとても慎重になる。
1週間ぶりの操業が決まり、早朝の港に集まり始めた漁師さんたち。漁が始まる合図である、旗が上がるのを待っていましたといった様子で、一気に30隻ほどの船が出航していった。昆布漁の道具はたったひとつ。約4メートルの棒の先端に付いたL字のカギだ。そのカギで昆布を引っ掛け、自分の腕に巻きつけて引き上げる。量を多くとるのではなく、光に当たってしっかりと光合成をして育っている品質の良い昆布を狙っているのだとベテラン漁師の築山つきやまさんが教えてくれた。
水揚げされた昆布は漁師さん各自が持つ干場に次々と運ばれ、その日の潮風の流れに沿って一本一本丁寧に並べられていく。乾燥させるときに重なってしまうと、くっついた痕が残ってしまったり、しっかりと乾燥されず、品質の低下につながるので、乾燥作業はとても慎重な作業だ。真っ直ぐに並べられ、真っ黒に輝く昆布には、えりもの漁師さんの品質へのこだわりがあるのだ。















