
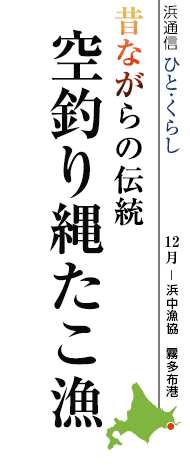
子蛸と水蛸。霧多布で穫れるたこは大きく分けると2種類。地域によっては子蛸のことを柳蛸、水蛸のメスを真蛸と呼ぶこともあるという。柔らかい子蛸は「たこのかき揚げ」、食感の良い水蛸は「お刺身」や「しゃぶしゃぶ」がオススメ。たこによってもいろんな特徴があるので、たくさんの人に美味しく食べてもらいたいと漁師さんは言う。たこの種類やオス・メスの選別を一瞬で行うベテランの漁師さんによって、水揚げ作業はあっという間に行われていった。
天候が良ければ、出港は早朝3時で帰港は夕方4時ごろ。2時間ほどかけて漁場に移動し、2、3週間前に仕掛けておいた縄をあげて戻ってくる。船の上では選別作業があり、帰港後すぐに水揚げし、その日の片付けと次の日の準備。これでやっと朝まで休めるのかと尋ねると「明日は天気が悪くなりそうだから、夜中に出港するよ」と、船頭さんはスマホの天気予報をチェックしながら言った。この数年のスマホの普及で漁の作業は大きく変化したのだという。アプリでピンポイントの天気予報を知ることができるので、出港して天気が悪くなったから引き返してくる「空操業」はほとんどなくなった。LINEによって一括連絡が出来るようになったおかげで、たくさんいる乗組員への出港時間の連絡がとても簡単になり、一人一人に電話連絡してた時間のロスも無くなった。かなり便利になったのだ。スマホの普及が漁師さんの業務の効率化に影響していた。これからの時代、どんな些細なことでも新しいことに取り組まなくてはいけないし、なるべく乗組員の負担も減らさなくてはいけなと船頭さんはいう。霧多布では30年以上前から、資源保護のためにたこの産卵礁を作るなど、増殖に対して取り組んでいる。新しいことを取り入れながら、資源を守ることによって、近年はたこの水揚げ量は増加しているそうだ。昔からの取り組みが今に繋がっているのだろう。















