
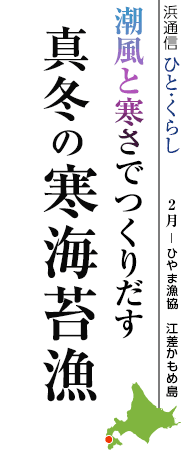
強い磯の香りを特徴に持つ、かもめ島の寒海苔。島を上から覗き込むと、かもめが羽根を広げているように見えることから「かもめ島」と呼ばれ、天然の岩海苔漁場となっている。海水をかぶりながらも、水面上にあらわれる千畳敷の岩場には、近づくだけで独特な磯の香りが漂う。ミネラルたっぷりの海水が染み込んだ、ザラザラとした火山岩の岩場。だからこそ、磯香りが強い海苔が育つのだろう。
岩場にびっしりとついている海苔を見ると、資源豊かでたくさんの生産量があるのかと勘違いしてしまいそうだ。実際は海苔漁師さんの作業は全てが手作業で、驚くほどの手間がかかっているため、大量生産は難しい。腰を曲げながら、先がL字になった道具「カギ」を使い、岩に張り付いた海苔を黙々と摘み採り続ける漁師さん。摘み採る重要なポイントは太陽の日差しと潮風! 条件がそろって、岩場で乾燥した海苔にカギを引っ掛けてめくり採るのだと教えてくれた。状態が良いと1メートルほどの長さで剥がれるが、逆に雪降りや風のない日は、海苔が湿り滑ってしまうため全く剥がれない。そんな日の漁はお休みになってしまう。厳しい条件が揃わないとできないのが海苔漁だが、冬の凍てつく浜風がある江差だからこそ、海苔の生産地として大きな強みとなっているのだろう。
摘採してから、海苔に付いている小石を洗い取り、包丁で細く刻み、長方形に形成する作業を「打つ」という。海苔打ちは簡単に見えてとても難しく、和紙を作るように、すだれに型をあてて海苔を均等に伸ばし、型を外した後はすだれのまま寒風させる。穴があいたり、均等な厚さにならないと等級が下がってしまう。隙間なく真っ黒な海苔を整えるのは、高い技術が必要な職人技。気の抜けない作業だ。それに加えて重要なのが乾燥させる時の「凍しばれ」。氷点下の寒さで海苔が凍ったまま乾燥することによって、縮まずに隙間のない1等級の海苔が出来上がるのだ。
太陽の日差し、潮風、凍れ。これらの条件と漁師さんの細かな手作業によって作られる寒海苔。また食べたくなる風味と、限られた季節にしか採れない高級品として根強い人気を誇っている。















