
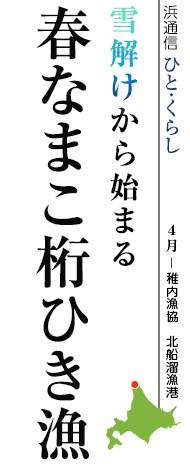
稚内では資源保護の取り組みで、産卵期を避けるため春の操業は3、4月のみ。暖かくなると活発に動き始めるなまこの習性を把握しているからこその春の漁。稚内の漁師さんの一年は春のなまこ漁から始まる。
「八尺」と呼ばれる3メールほどの櫛の形をした道具に網を付け、海底におろしてなまこを漁獲する桁(けた)ひき漁。この桁ひき漁はとても難しいという。漁場によっては海底約20メートルから深いところでは50メートル以上の場所もあるので、地形によって漁師さんの様々な工夫がある。魚探にもレーダにも映らないので、頼れるのは漁師さんの経験のみ。海の地形や、潮の流れ、その日の天候を読みながら行っている。今までの経験を頼りに行う漁だからこそ、獲れない時は本当に悔しく、次の漁のために工夫をするという。道具の仕掛け方や網の長さなど、先輩漁師の真似をして改善をしていく。自分の経験値を上げながら漁師さんは成長しなくてはいけないのだ。 漁師さんの努力は獲るだけではない。産卵期には採卵し、8月に種苗なまこを海に放流する、「育てる漁業」に積極的に取り組んでいる。商品になるまでに育つのは約5年。110g未満の小さななまこは海に戻すのを徹底し、漁師さんが自宅用に獲ることも絶対にしない。稚内の漁師一人ひとりの意識が大切だと教えてくれた。
稚内のなまこは乾燥した時に、ねじれや変形が少なく買い手からの評価が高いそうだ。水温が低いため稚内産の成長は遅いと言われているが、寒さの中でゆっくりと大きくなるのが、品質の良いなまこができる理由かもしれない。高級品として高値で売買されているからこそ、目先の利益で考えるのではなく、これからの続く資源として育てる意識が強いのだろう。















