
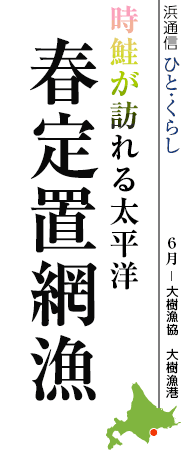
漁師さんの1日は番屋での朝ごはんから始まる。早朝5時半、大樹漁港の近くにある番屋へ、続々と車が集まってくる。テーブルにおかずと炊き上がったご飯が並ぶと、そこからは驚くほどあっという間!! 2、3分で朝ごはんを食べ終えて、港に向かい、出航までは息つく暇はない。ご飯を食べ始めてから15分ほどで漁船は定置網の漁場へと海を移動していた。
6月は北海道でも蝦夷梅雨と呼ばれる期間。大粒の雨が降っていたが、波が時化ていなければ雨は問題ではない。1隻に13名ほどの漁師さんが乗り込み、漁場につくと同時に、各自の持ち場へと移動。あっという間に海に下ろしていた定置網を引き上げる。ほとんどの作業がアイコンタクトで進んでいく。機械を使うようになったとはいえ、網の引き上げには全身を使い、漁師さん全員が呼吸を揃えながらの作業が行われていた。雨が降っていたため海水は濁り、網の中に時鮭がいるかどうかは引き上げて見ないとわからない。そんな中からキラリと光る時鮭の銀鱗が見えると、網を掴む手により一層力が入るのだろう。
脂がのった時鮭の身は、驚くほどに旨い。春夏の高級食材と呼ばれる「時鮭」が旨い理由は、産卵期を迎えていないだけではなく、もう一つ欠かせない理由がある。船の上で行う「活〆」だ。多い時には数千本獲れる時鮭を、網からあげるとすぐにエラを切り、船底の水槽で泳がせて血抜きをする。一つ一つが手作業でとても手間がかかるが、活〆をすることで水揚げした後の鮭の味が全く違うのだ。
昔、まだ船上で活〆をしていなかった頃、アザラシに頭だけを食べられた時鮭を、漁師さんが自宅で食べて、いつもよりも格別に美味しいと感じた。今考えると、頭を食べられたことによって海の中で血抜きがされて美味しくなったのだろうと教えてくれた。手間がかかる作業だが、鮮度の良い時鮭をみんなに食べてもらうには「活〆」は定置網漁では絶対欠かせないのだと漁師さんはいう。















