
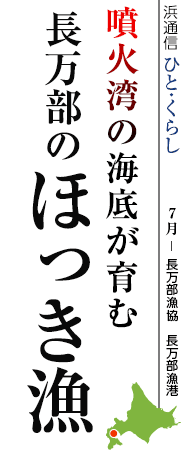
7月。陽が昇った4時。出港した船は西へ向かって行く。目指すは国縫くんぬい方面の沖合だ。噴火湾は長万部、はるか続く砂浜の沖の海底、特に国縫沖はミネラル豊富な砂鉄混じりの海底が広がっている!そこで育つほっきは砂鉄のように真っ黒に彩られ、赤ほっき・茶ほっきと呼ばれる通常のほっきとは全く別種のようだ。それほどインパクトがある。
漁場へ着いた船は漁具を沈め作業を始める。ここではほっきの貝殻を傷つけないように噴流式マンガンと呼ばれる漁具・手法をとっている。網の前部にあるマンガンという道具にホースが設置されていて、そこから海水が勢い良く噴き出され、その水流で海底のほっきが浮き上がったところをタイミングよく網が受け取るといった具合だ。
砂鉄は少し深い海底の方が多く、黒ほっきが生息できるのは水深が5~8メートルラインだという。それより浅い3~4メートルラインで獲れるのは褐色の赤ほっきだ。もちろんこの赤ほっきの味も折り紙付きの絶品だ。
6時間程操業して11時頃には帰港となり、港ではクレーンを使って荷揚げされる。大人の握りこぶしより大きな貝が網に、箱にびっしりと山積みされている。その迫力はなかなか目に出来ない光景だ。そして何より、真っ黒に光る黒ほっきのその存在感たるや、「すごい」と自然に言葉が出てくるほど。
丁寧に荷揚げされたほっきは色・形・サイズで選別され、重量を計り、氷で冷やされ、あっという間にトラックに積まれ出荷されていく。どこの港でも展開される光景だが、その迅速さは他にはないほど。鮮度抜群のほっきが食せる理由のひとつがこの手際の良さなのだと感じた。
長万部の黒ほっき貝は、鉄分をはじめとしたミネラル豊富な海底に育まれている。その大きく真っ黒な貝の中には肉厚の身がみっちりと詰まっている。
長万部の海は、生で食せばコリコリとした食感にふくよかな甘味が口いっぱいに広がり、火を通せば逆に柔らかく旨味が口いっぱいに広がるほっきがくれる幸せで満ちあふれていた。

















