
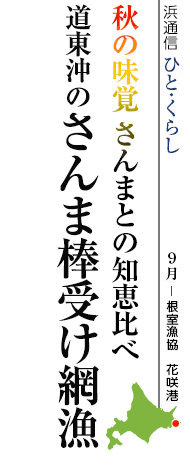
7月下旬、いよいよさんま漁が解禁になる。しかし、その頃のさんまは過ごしやすい冷たい海水(8~11度)を求めて日本からはるか遠いロシア海域を回遊しているため、実際に漁になるのは、餌を求めて回遊しながら次第に南下し北海道に近くなる8月下旬頃からだ。とは言え北海道の東海域はるか遠くが漁場となっており、大型船でも1日半はかかるエリアだ。
9月。秋風が吹くようになると、さんま漁が本格的になり、花咲港は全国から集まったさんま船で活気に溢れる。
花咲港を出港した船は1日以上かかる漁場へ向かう。漁場では魚群探知機でさんまを探し、日が落ち暗くなると、漁師さんとさんまの知恵比べがはじまる。
棒受け漁とは、さんまの 光に反応して移動する走光性という習性を利用した漁で、真っ暗な海面へまばゆい集魚灯をあててさんまを寄せ、その寄ったところを網でまさに一網打尽で漁獲する方法だが、そこには漁師さんとさんまの駆け引きが展開されている。
まず、集魚灯を右舷だけ点灯させ、そこにさんまをどんどん寄せる。十分な量が右舷側に寄ったところで、左舷側に網を仕掛ける(沈める)。次に右舷の明かりを一列一列消していき、同時に船の先を点灯させ、さらにサーチライトを利用し寄ったさんまをどんどん左舷側へ寄せて追い込んでいく。網が沈められている左舷側にさんまが寄ったところで明るい集魚灯の色を暗い赤色にすると、さんまが急に沸騰した鍋のように海面で沸き立つ。その次の瞬間に網を手繰り寄せると大量のさんまが捕獲できるというわけだ。それをフッィシュポンプで吸い上げ同時に氷漬けにする。そして、獲ったさんまの量と海の模様を見ながら操業を切り上げて帰港になる。もちろん1日半かかる。
港に戻った船は競りの時間に合わせて荷揚げし(通常競りは1日に朝7時、11時、13時、15時と4度行われている)、それが終わると給油、氷の補給などを済ませ、一時たりとも休む暇もなくすぐに漁場へ向けて出船する。これが11月末くらいまで続けられる。本当に大変な仕事だ。
さんま資源を維持するために多くの規制がある中で、漁師さんたちは、多くの方に美味しいさんまを食べてもらいたいと数ヶ月に渡り、はるか沖で操業を続けている。陸にいる時間は台風などで漁場へ行けない場合くらいだ。
天高く馬肥ゆる秋の食卓を飾るさんま。そのさんまには漁師さん方をはじめ多くの関係者の熱い思いが込められていた。

















