
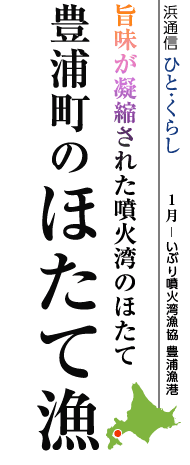
息が真っ白になる中、岸壁では忙しく「おかまり」さん(陸周りさん が おかまり と訛って転用された語で陸作業を行う人々のこと)方が準備をしている。そうこうしていると次々にほたてを積んだ船が入ってきて接岸する。大きな網の中にはほたてがびっしりだ。港から沖へ10分ほどの海域にある養殖施設で、ほたては海中に吊されるように設置されている。それを回収してくるわけだ。
ここ豊浦町は噴火湾ほたて養殖発祥の町で、礼文華地区がその地だという。海流等の関係で、ほたてが食べるプランクトンが豊富かつ海も荒れにくく、ほたての養殖場にとても適しているという。そして礼文華地区沖にてほたての養殖が始められてから50年以上が経つ。この間にその養殖技術は向上し、漁の方法も進化してきて今がある。
接岸した船からほたてが入った網をクレーンで吊り上げて、「ミキ洗」または「ガラガラ」と呼ばれるほたての洗浄機へ投入される。ミキ洗のスイッチが入るとガランガランと大きな音が辺り一面に響く。水揚げされたばかりのほたてには、イガイやフジツボ、イソギンチャクらがびっしりとついている。この洗浄機はそれらを洗い落としてくれ、かつサイズで仕分けてくれる多機能マシーンだ。
投入されたほたては回転するドラムの中を通ってくるが、その間に貝の付着物が取り除かれ、きれいになってサイズ別に出て来る。それを一瞬でチェックして、無事に通過したほたてが移送トラックにベルトコンベアーで運ばれていく。また一方では、ほたてを吊っていたロープを専用の器具で巻き取る作業が行われる。全てに無駄がなく、隙がない作業が続く。
船上のほたてが全てきれいになると2トン車にいっぱいになった。ここまで約2時間。それから再び沖へ出て、今度は「丸カゴ」と呼ばれる網カゴの中で特別に育てられているほたてを回収してくる。戻ってきた船からほたては直接岸壁へ丁寧に広げられ、ここから船員・おかまりさん方総出で人力による貝の洗浄が始まる。専用の小型の鉈なたで、ほたてに付着しているイガイなどを丁寧に削りとる。目の前にはほたての山。その山がなくなるまでに総出でも2時間近くかかった。これは貝のままの直接販売分とのことだ。洗浄機を通すとどうしても貝が欠けたりするので、そうならないためにはやはりひとつひとつ丁寧に作業するのが賢明である、ということだ。そして9時に先のミキ洗経由のほたての検量がなされ、入札がはじまる。同時に直接販売分の荷造りも行われる。とにかく一瞬たりとも手を休める者など一人もいない。なんというチームワークだろうか。
なお、このほたて漁は3月いっぱいまで続けられる。
海と山の幸が豊かな内浦湾(噴火湾)という意味で豊浦という町の名になったというように、ここ豊浦町には海とほたてを知り尽くした漁師さん方が育てた、旨味がぎゅうっと凝縮された超絶品のほたてがあった。

















