
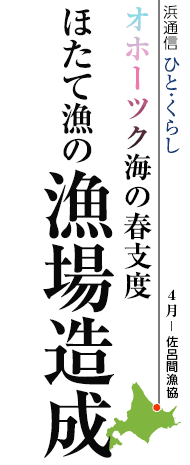
佐呂間で獲れるほたては、外海で育つ天然ものと湖の中で育てる養殖の2つがある。天然といっても、海区を分けて計画的に整備し、稚貝を放流し漁獲しているのので、手をかけていないわけではない。限られた天然の資源を大切にするためにも、この時期の漁場造成は大切な作業だ。
早朝にはマイナス5度まで下がる4月の佐呂間町。サロマ湖に張った氷はまだ溶けず、寒い春が続いていた。湖は凍っているが、ほたて漁でこの時期に必ずやらなくてはいけないのが、サロマ外海の漁場造成だ。
漁場造成とは、5月の稚貝放流に向けて漁場を綺麗に整えること。佐呂間漁協では、湖から海に出た付近をAからDまでの4海区にわけて、1年1海区で稚貝放流を行い、3年後に漁獲している。4つの海区を計画的に使うことにより、3年かけてしっかりと身入りしたほたてに育てるためだ。そのためにも、稚貝を撒く前の3月下旬から5月にかけて、前年に獲り残したほたてや、天敵となるヒトデなどを除去している。獲り残したままにすると、ほとんどのほたてが死んでしまい、新しく放流した稚貝にとっても良い環境にならない。
作業としては桁引き網漁と同じで漁法で、大きな熊手のような八尺に網をつけて、海底を数百メートルひいて漁獲する。昨年の獲り残しと言っても、1隻の船が1日で水揚げするのは約10トンもあるので、作業もかなりの体力が必要となる。そんな漁師さんの努力で行われている漁場造成によって、海底質改善された佐呂間の外海。そこで育つほたては、オホーツクの栄養をたっぷり蓄えたことにより、旨味が濃厚でプリプリに育っているのだ。
オホーツク海は流氷によって多くのプランクトンが運ばれ、栄養豊かな漁場ではあるが、それに頼るだけではない。漁師さんの計画的な漁場造成によって、資源を生かす漁へとなっている。漁場になる海底の質を改善することが、6月からの本操業への実りとなり、沿岸漁業をしっかりと活用した生産体制として確立しているのだろう。















