
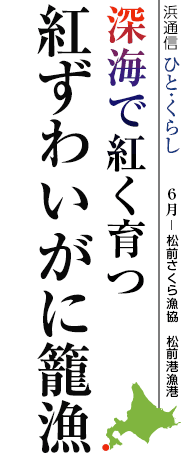
たらばがにや毛がにが水深約250メートルで育つのに比べて、 ずわいがには約1,400m の海底に生息している。 太陽の光が届かない深海は季節にかかわらず水温が2度前後 とかなり冷たい。 過酷な環境とも言われているが、 冷たい海の底でじっくりと育つから こその美味しさが紅ずわいがににはあるのだろう。
紅ずわいがには呼び名のとおり、海中で生きている時から鮮やかな紅色の甲羅をしている。紅あかい甲羅と長い足で移動しながら深海の底で生息しているのだ。そんなかにをつかまえる漁法が「かに籠漁」。大きな円型の籠にさばやにしんなどの餌をつけて深い海に沈め、数日後に籠を引き上げると、中には綺麗な紅い色のかにたちが入っている。まるで茹で揚げたような紅い甲羅は、まさしく「紅ずわいがに」だと漁師さんは言う。
かに籠漁は、出航してから港に戻ってくるのが3日後。海がまだ暗い深夜に出航し、数時間かけて漁場へと移動すると、数日前に仕掛けておいた籠を引き揚げる。深海から揚げられたかには、船の上でM、L、2Lの3サイズに選別され、船の底にある大きな冷蔵庫へと運ばれる。そして、また餌を仕掛けた籠を海に沈めておくのだ。水揚げの際、海底1000メートル以上の深さから引き揚げると、水圧の変化によりかにみそが出てしまう。かにみそがこぼれるのを防ぐため、すべてのかにはお腹を上にひっくり返った状態で、コンテナに詰め込まれていた。深海で生息する紅ずわいがにならではの水揚げ風景だ。
深い海で育つかにたちが、漁獲できるサイズになるまでは約8年かかる。そんな環境を知っているからこそ、漁師さんは資源保護のため甲羅9.5センチ以下のサイズは海に放流して大きくなるのをじっくりと待っているのだ。貴重な資源を守るために、漁期は3月からスタートし、夏の8月に終了。その年の漁期の漁獲量は決められているので、一度の出航で水揚げする量を計算し想定している。継続的な漁業を大切にしているからこそのこだわりだろう。















